コンタクトセンターの「コンサル」×「分析」×「教育」の3人のコラボです
2月27日に、私が、その一部を書きました『図解でわかるコンタクトセンターの作り方・運用の仕方』が出版されます。
本書は、長年にわたりコンタクトセンター業界を牽引されているアドバンス・コンサルティングの 有山 裕孝 さんの企画に、AIやテキストアナリティクスの分析家である市瀬 眞 さんが賛同され、当社でSV教育の企画・開発をおこなってきた私もお誘いいただき、3人で書きました。
本書の打ち合わせが始まったのは、コロナ以前のこと。2020年4月の緊急事態宣言下は、ステイホームで執筆真っただ中でした。対面接客が制限される中、コンタクトセンターの需要が高まると同時に、コンタクトセンターの在宅化も急激に進みました。本書には31の事例が載っていますが、急遽取材依頼を申し入れ、コロナ禍で在宅センターを立ち上げた最新事例も含まれています。
本書は、次のような構成です。
第1部 コンタクトセンターはどうあるべきか
1章 企業ミッションとセンターミッション
2章 コンタクトセンターとカスタマーエクスペリエンス
第2部 コンタクトセンターの作り方と運用の仕方
3章 コンタクトセンターのオペレーション設計
4章 組織作りとコミュニケーターの育成
5章 コンタクトセンターのマネジメント
6章 コンタクトセンターを支援するソリューションを知る
第3部 コンタクトセンターの改善・高度化の進め方
7章 コンタクトセンターの運用では、日々、改善と改革の努力を怠らない
8章 様々なサービス・技術をいかに活用するか
9章 最新のコンタクトセンターを支えるテクノロジー
10章 コンタクトセンターの将来展望を考える
思い出してみれば、それは超「現場ドリブン」だった
1章から5章のコンタクトセンターの基本設計や運営に関わる部分は私が書いています。
コンタクトセンターの仕事にたずさわって20年以上が過ぎましたが、そのうちの半分はSV教育をしてきました。だから、このパートは当社で作ってきたSV研修の教材が元になっています。
SV教育を始めた頃を振り返ってみると、それは「フィードバックのステップ」をまとめたことから始まったことを思い出しました。ここでいう「フィードバック」とはSVがオペレーターに改善指導する別名「1on1」とか「コーチング」とか言うアレです。
なぜ「フィードバックのステップ」から整理したかといえば、その頃、あちこちのセンターで、ベテランSVが後輩SVのために「フィードバックマニュアル」なるものをとても苦労して作っていたのです。ベテランSVが後輩SVのためにマニュアルを作る、なんて美しい光景でしょう。
でも、そんなにうまくはいかないんです。思いが先行して一般化しきれなかったり、語れるんだけど文字にはできなかったり、遅々として進まず、ただただもがいて時間が過ぎているSVたちの様子も目にしました。そこで、皆さんが作りかけているマニュアルを寄せ集め、そこからイイトコドリさせてもらって「スタンダードなステップ」としてまとめたのです。ここからSV研修づくりはスタートしました。
現場で活躍するベテランSVたちの声を集めて作られた研修。これって、超、現場ドリブンですね。そして以後しばらくの間、当社のSV研修の教材は、こうして現場のベテランSVの声を集めて作ってきました。
良質なたたき台があれば、レベルアップは早い
スタンダードな「フィードバックのステップ」を作った結果、どうなったのか。それをたたき台にして「うちのセンターはもっとこうした方が良い」というレベルアップした意見交換がされるようになりました。作るのは苦しくて時間がかかりますが、たたき台があれば、議論は軽やかに活性化するのです。そしてそれは、教育効果を高め、成長速度を早めます。
本書にも「フィードバックのステップ」が載っています。10年前に書いたものとはだいぶ姿を変えていますが、そのときのエッセンスはしっかり残っているんじゃないかと思います。この他にも、「スクリプトの作り方」、「稼働管理の考え方」、リアルタイムでの「ブースコントロール」手法など、現場のノウハウを元に築き上げてきた基本的な考え方、やり方が書かれています。ぜひ、各センターのSV教育の教科書として本書を活用いただけると幸いです。
「この本にはこう書いてあるけど、うちのセンターはちょっと違うな、うちのスクリプトはこうあるべきだ!」と、センター長がSVに語る。この本をきっかけに、そんな光景が生まれてくれれば、私にとってこれほど嬉しいことはありません。
おそるべし。有山さんの人脈。最新技術を活用した豊富な事例
6章から8章、そして最後の10章は、発起人である有山さんが執筆されています。有山さんは大規模コンタクトセンターへのシステム導入や、構築・運用、業務改善など、長年にわたってコンサルティングをされています。
既に皆さんにとっては当たり前となっている各種システムについて、知ってそうで知らない基本から、知られざる裏側までを教えてくれます。そして最新技術を活用して、いかにコンタクトセンターを高度化していくかについての考察と共に、ニッセン、ショップジャパン、チューリッヒ保険、NTTコミュニケーションズ、日本航空、LIXILなど、他にもたくさん、全部で31の事例は、きっとみなさんにご満足いただけると思います。
市瀬さんはコンタクトセンターと最新技術の架け橋だ
もう一人の共著者である市瀬さんは、大手通信会社でシステム開発のプロジェクトマネージャーを務めながらも、立命館大学情報理工学部で毎年講演をおこなう自然言語処理技術や人工知能技術の専門家です。担当された9章は、この章だけで80ページを超える満足のボリュームです。
AI、音声認識、テキストアナリティクス等、最新技術の解説はもちろんのこと、それをコンタクトセンターのどのような場面で活用できるのか。うまく活用するにはどうしたら良いかを、豊富なご経験からの洞察を含めて解説しています。コンタクトセンターを中で運用する人にとっても、コンタクトセンターを傍から支援する人にとっても、知っておいて得しかない内容です。
専門分野はそれぞれで、長年コンタクトセンターに関わってきた3人で書きました。皆さんのセンターの運営がより良いものになるよう、業務改善の視点から、新技術活用の視点から、人材教育の視点から、本書をお役立ていただけることと思います。
最後に、このような機会を創ってくださった有山さん、市瀬さん、取材協力に快く応じてくださったたくさんの企業の皆様に、改めて感謝申し上げます。
そして、度重なる修正に応じてくださったデザイナーの初見弘一さま、カッコいいカバーデザインをしてくれた萩原睦さま、この本をより一層、みなさまにとって、わかりやすい読みやすい本に仕上げてくださって、ありがとうございます。
そして、そして、その全てをとりまとめ、いつでも、誰にとっても強い味方となり、力強く出版まで導いてくださった 中尾淳 編集長、日本実業出版社の皆様に、心より感謝申し上げます。中尾さんと飲みに行ける日が、早く来ますように!
みなさまにとって、
本書がお役に立ちますように。
図解でわかるコンタクトセンターの作り方・運用の仕方 | 有山裕孝, 仲江洋美, 市瀬眞 |本 | 通販 | Amazon
Amazonで有山裕孝, 仲江洋美, 市瀬眞の図解でわかるコンタクトセンターの作り方・運用の仕方。アマゾンならポイント還元本が多数。有山裕孝, 仲江洋美, 市瀬眞作品ほか、お急ぎ便対象商品は...
その他関連サービス
■クライアント企業に合わせた、最適運用を実現
コールセンター・コンタクトセンター
■クライアント企業のマーケティング活動を最適化
アウトバウンド
■お客様のニーズに寄り添い、お客様に合わせたミライを提供
インバウンド



 資料ダウンロード
資料ダウンロード
 お問い合わせ
お問い合わせ




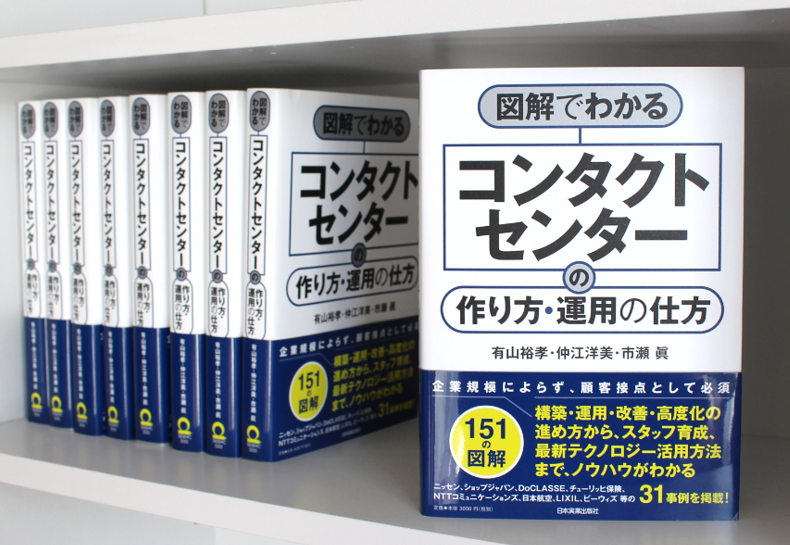

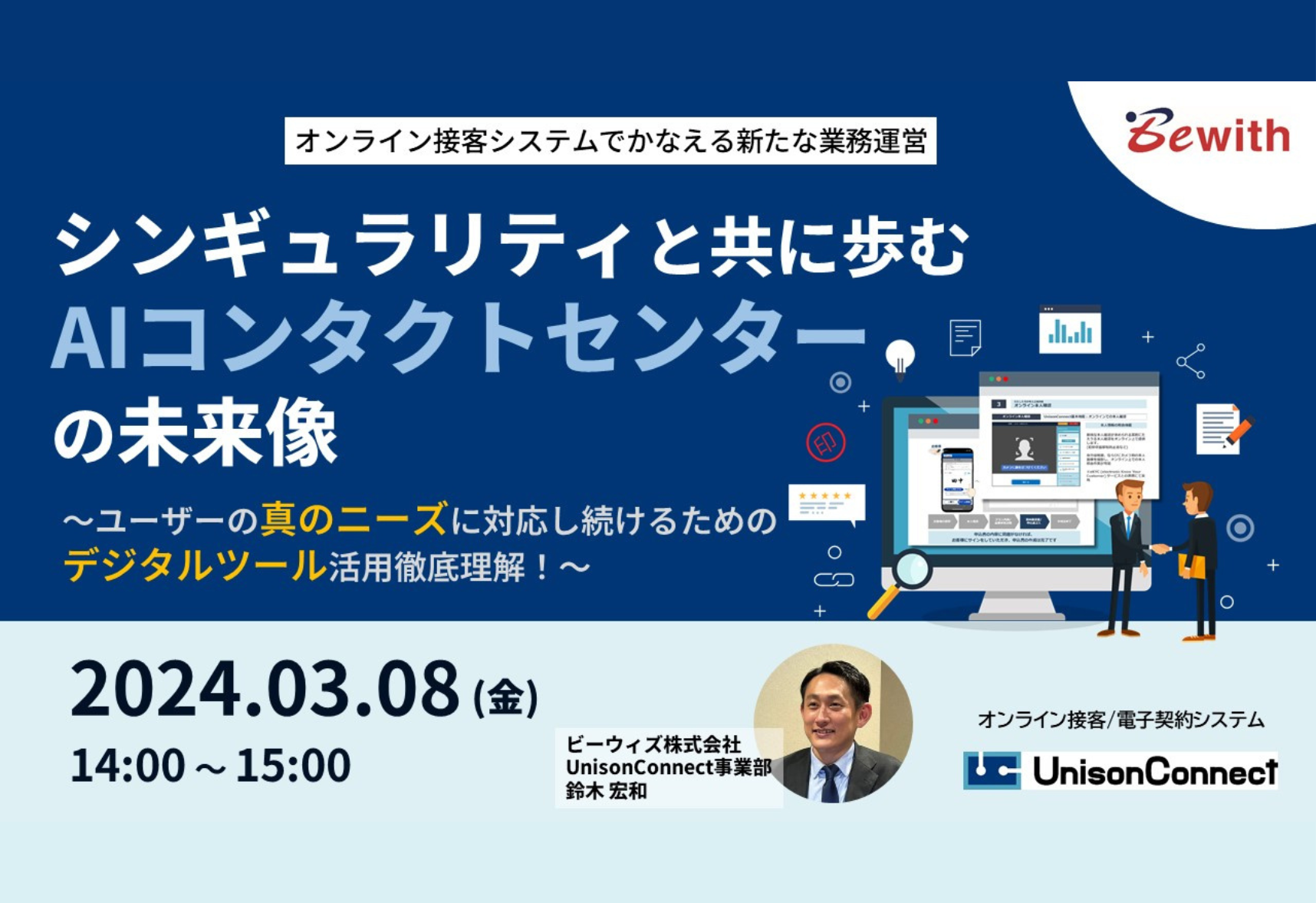


 メールマガジン登録(無料)
メールマガジン登録(無料).png)
.png)




