「モチベーションがなくなったので辞めます」
こう言って去っていくオペレーターは少なからずいる。
一体、モチベーションってなんだ。
自分の数少ないアルバイト経験を元に言うならば、仕事を探す時に重要な検索ワードは「場所」「時給」「職種」だった。自分にできそうで、必要な対価を手に入れられそうか。
現代で、特に有期雇用の仕事を探している人たちも大差ないのではないかと思う。
そして、有期雇用という形での仕事を希望するなら、それで良いと思っている。私たちSVがすべき大切な仕事の内の一つは、そういった経緯でコールセンターの仕事を選んでくれた方々が、正しく仕事を遂行できるよう、業務の標準化を推し進めることだ。
だから、最初から仕事内容そのものにモチベーションや情熱を持っていなくてもかまわない。そう思っている。
しかし実際には、モチベーションがない、あるいは失ったがために仕事を継続できない人たちがいる。研修を受け、トレーニングを乗り越え、せっかく電話が取れるようになったのに。これは残念なことだ。
今までに出会い、モチベーションを失って退職となってしまったオペレーターのため、そして今一緒に働いているオペレーターのために、今一度モチベーションについて考えてみたい。
仕事にモチベーションは必要か
モチベーションとは、広辞苑によると「①動機を与えること。動機づけ。誘因。②物事を行う意欲。やる気」のことを意味するという。
つまり、「モチベーションがなくなった」というのは、「意欲ややる気がなくなった」状態を指すのだろう。
元々私は、仕事をするためには、仕事に対する意欲ややる気など不要だと思っていた。なんなら今でも思っている。
人は生きなければならない。生きるためにはお金が必要で、それは仕事の対価として得るのが一般的だ。よって仕事をする。見事な三段論法だ。仕事を辞めるというのはそう簡単な決断ではない。
しかし現実には、モチベーションの喪失によって仕事を辞める人が一定数いる。
それはきっと、生きるためという理由だけでは、もう仕事を続けられないということだ。
モチベーションをなくしたとは
モチベーションをなくした、という退職理由は、新人オペレーターからはあまり聞かれず、中堅・ベテランオペレーターから発されることが多い。
確かに、オペレーターという仕事はモチベーション(=意欲・やる気)を維持しづらい。
最初はいい。業務の内容を理解し、自分がどのような対応をすべきかを理解し、話し方の練習をする。
研修を受けトレーニングをしている日々は、知識が増え続け、上手な言い回しが身に付き続ける。
そして、一人での応対開始直後もいいだろう。お客様からのお問い合わせに初めて一人で回答できた。やってみたら意外とできる。この間覚えたばかりのことをお伝えしたら、お客様にご理解いただけた。日々、少しずつ達成感を得ることができる。毎日が成長だ。
しかし、オペレーターの仕事を開始して半年、1年経ったらどうだろう。
最初は、お客様のお問い合わせに対し、一人で対応を完結することができただけで嬉しかったし、達成感が得られたのに、中堅からベテランオペレーターになれば、それが普通のことになる。場合によっては、達成すべきKPIを求められ、そこに到達できていないとSVから指導を受けることになる。自分が「できている」ことよりも、「できていない」ことに目を向ける機会の方が多くなる 。
変化もなく、自分の「できていない」ことに目を向ける日々は、確かに辛い。
誤解無きようお願いしたいのは、オペレーターは自分で実感できていなくても、間違いなく日々その対応を進化させているということだ。経験を積んだだけ自己完結率が高まっているし、説明もスマートになっている。日本語として正しくない言い回しが、センター内で爆発的に流行する事象はコールセンターあるあるだが、それだってオペレーターが進化しようとしている証と言える。
ただそれでも、オペレーター自身では成長が実感しづらいのが実情で、変化のない日々が連なっていることにどうしても気持ちを維持できなくなり、仕事をする意味を見失ったときに「モチベーションがなくなったので辞めます」という言葉が発される。
最もモチベーションが低下した時に思いつく言葉が「モチベーション」であるとは、なんとも皮肉だ。
モチベーションとES施策とハロウィンと
ここで少しお勉強の話をしたい。ハーズバーグ氏の唱えた「二要因理論」だ。
要すれば、仕事に対する満足度は、何か特定の要因を満たせば上がり、不足すれば下がるというものではなく、満足に関わる要因と不満足に関わる要因がそれぞれ存在する、というものである。
満足に関わる要因は「動機付け要因」と言われ、「達成・承認・仕事内容・責任・昇進」がそれに当たり、不満足に関わる要因は「衛生要因」と言われ、「給与・福利厚生・経営方針・管理体制・人間関係・監督方法」がそれに当たる。このあたりは多くのサイトに情報が掲載されているため、ご興味のある方はぜひご覧いただきたい。
私たちがオペレーターのモチベーション向上のためにES施策を考える際、真っ先に考えてしまうのは衛生要因に関する事柄だ。
ハロウィンが近くなればセンターをデコレーションし、有志が仮装をして電話を取る、入電が激増して忙しくなればお菓子を渡して労う、クリスマスになればツリーを飾る。みんなで一つのイベントを経験して楽しみ、人間関係を強めていく。もちろん大事だ。斯く言う私も、ハロウィンには頭に包丁を突き刺した姿でSV席に座っていた。
でもきっと、それだけではオペレーターのモチベーション回復には至らない。なぜなら、オペレーターが感じている「モチベーションの喪失」は、衛生要因の不足に起因するものだけではなく、達成感のなさ、承認されている感じのなさという、動機付け要因の不足もその原因だからだ。
オペレーターの「達成感のなさ」「承認されている感じの不足」から生まれる無力感は、日々大きくなる。
それに対し、年に何回か行われるES施策のイベントでは圧倒的に不足だ。不足だし、そもそも対策を取るべき要因を見誤っている。日々積み重なるものは、正しい対策で日々突き崩していかなければならない。
職場が楽しくあればいいという考えだけに囚われるのはもうやめよう。オペレーターは毎日仕事をしに会社に来ている。私たちはそれを忘れてはいけない。
モチベーションを失わないためには
私の中に、オペレーターがモチベーションを失わないための施策として、二つの仮説がある。
一つ目は、日々オペレーターに声をかけること。
モチベーションを失うオペレーターは、日々の業務の中で達成感を得られていない。それどころか、誰からも見られてすらいないと感じている。たぶん。
だから、オペレーターとの関わりの中で気づいたことを、常に声を出して伝えてみてほしい。ちょっとしたことでいい。感謝や賞賛が伝えられれば尚良いし、実は賞賛じゃなくても良い。
「さっきのクロージング、良かったね」「今の説明、複雑だったのによくご理解いただけたね」「なに、今日声明るいじゃん」「ついに『恐れ入ります』って言えるようになったね」「平均であと2秒縮めれば達成できるよ」「今月寝坊何回目!?」「この間もお腹痛いって言ってた」「おねがい、あと1時間だけ。おねがい」
なんだっていい。
オペレーターが少しでも変化していることを伝えることができたなら、それは達成の確認につながるし、日頃の行為に触れることができたなら、それはあなたが必要だというメッセージになる。はずだ。
そして二つ目は、コールセンターは企業が提供する商品やサービスの一部であることを常に伝えていくこと。
コールセンターの仕事は、どうしてもボリュームで考えがちだ。何件のお問い合わせを何人で対応するのか、1件の対応を何分で完了させるのか。確かにこの視点は運営側にとって必要だが、オペレーターにとって大切なのはそこではない。
オペレーターによるお客様対応は、企業が提供するサービスの一部であり、オペレーターが対応した結果が、企業の成果に確実につながっているということ。そのことを具体的に伝え続けていかなければならない。
オペレーターが商品不具合時のサポートをしてくれるから、エンドユーザーは安心して商品を使用でき、オペレーターが商品の説明と購入方法の案内をしてくれるから、企業は売上を確保できている。
オペレーターの仕事が企業の活動や延いては社会と密接につながっていて、その大きなうねりの一部を成しているということを理解できるだけで、仕事の意義を見いだしやすくなる。はずだ。
どうだろう。これらが実践できるようになれば、モチベーションを失くして辞めていった人たちも、また一緒に仕事をしてくれるだろうか。
みなさんも、まずは近くのオペレーターに声をかけてみてほしい。きっとその中には、あなたの言葉に救われるオペレーターがいるはずだ。
ビーウィズでは、コールセンター教育を効率化し、オペレーターの成長サイクルを高める教育プラットフォーム『Qua-cle(クオクル)』をご提供しております。
コンタクトセンターにおける応対品質の課題を解決するために必要な、「学び」・「トレーニング」・「フィードバック」の一連のサイクルを実現する、コールセンター向け品質改善プラットフォームで、eラーニングから学ぶだけではなく、フィードバックのサイクルまでを組み込んだことが最大の特徴です。
また、モニタリング自動評価機能を搭載し、日常の自分の成果を確認することができ、オペレーターの成長機会に繋がります。
詳しい資料は、以下からご覧いただけます。
https://www.bewith.net/gemba-driven/download/entry-130.html



 資料ダウンロード
資料ダウンロード
 お問い合わせ
お問い合わせ






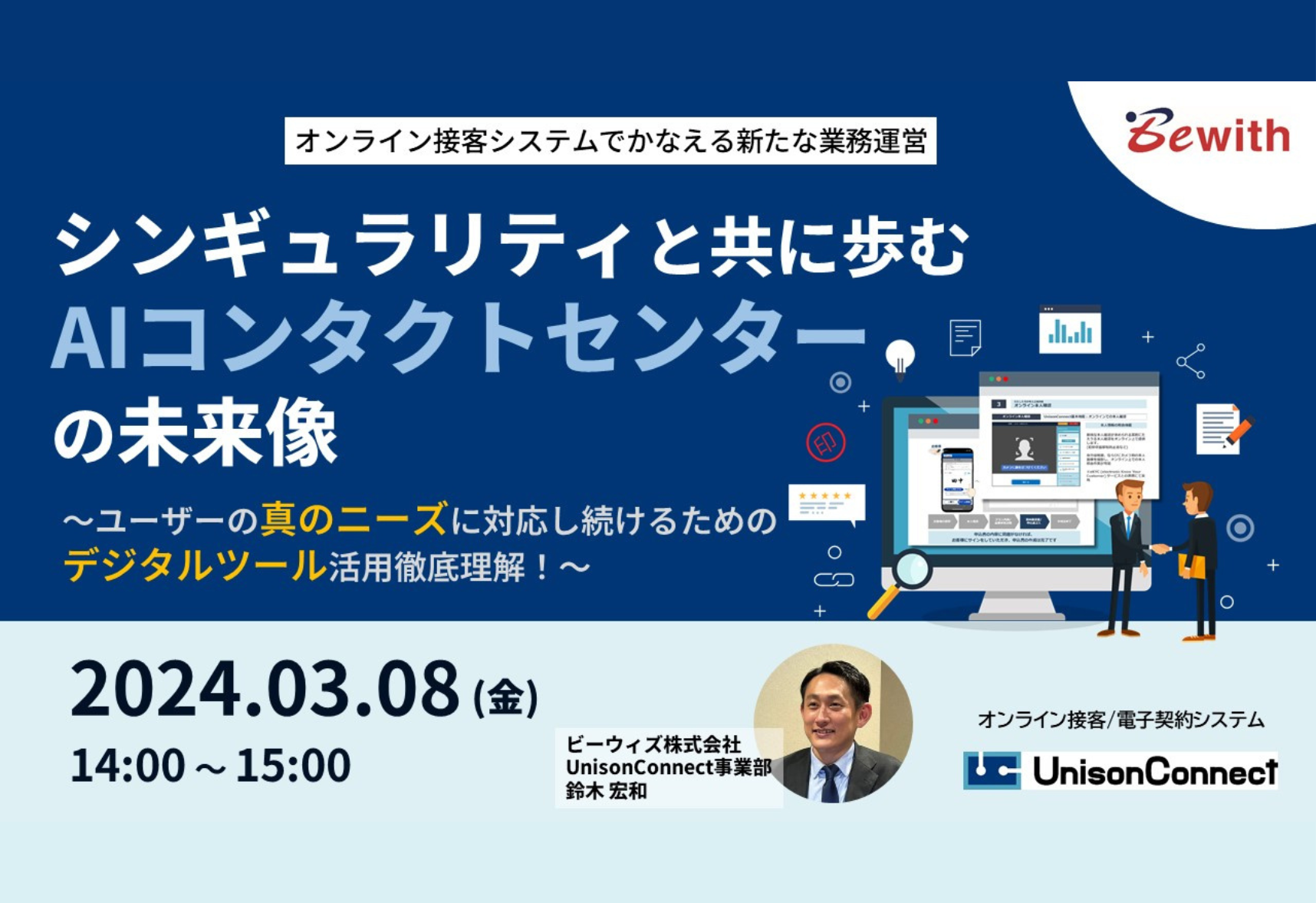


 メールマガジン登録(無料)
メールマガジン登録(無料).png)
.png)




