まずは絵を描く
前回登場したお茶の水さんは、私の社会人歴スタートの怒涛の2-3年を彩ってくれた方ですが、印象深い教えのひとつは、「まずは絵を描いてみよ」、でした。
PBXという電話システムが全く具体的なものとして認識できない当時、何度も図を描くことによってPBXを自分のものとして取り込む作業を行い、構築の現場で実物を見て驚きと納得を繰り返す。
この「絵を描く」という行為は、例えばパワポを使って図を書くということではなく、手書きをしてみる、ということなのです。
実はお茶の水さんはパワポが苦手で、真っ白な紙にご丁寧に定規を使ってきちきちっとした絵を描き、それをパワポにして頂戴、というリクエストを出すような人だったので、「デジタルで書けないだけじゃないですか~」ってブーブー言っていましたが、今思うとこの手で描いていく作業は提案書作成等、多くのシーンで役にたっているな、と思ったりします。
さて、PBXの設計において描く絵というのは、大胆に単純化するとこんな感じです。
改めて見ると自分で描いた絵の素朴感が否めないのですが、「中継方式図」とか言われることもあるこのような図は、必要な構成情報を見て取れるものですね。
大きく分けるとNTTなどの公衆網につながる電話回線を収容するTrunk(トランク)と呼ばれる部分①と、電話機などをつなげるStation(ステーション)と言われる内線収容する部分②で構成されます。
実際には利用するPBXやクラウド利用などにより構成は複雑化していきます。
ここに外線数、内線数を記載していきますが、私が関わっているOmnia LINK 導入提案の営業の現場では、既存のPBX環境における外線数と内線数を確認して、その数量をもとに費用を算出したりします。
ただ、ここは結構重要な気がしていますが、せっかくのリプレイスのタイミングであれば、現在の回線数や内線数が適切か改めて試算してみて、その結果に基づいてシステム選定の検討をするようなことがあってもいいのではないかと思います。
現行とのコスト比較という点でリプレイス検討を行うことが多いので、そこまでの試算を行うことは難しいこともわかりつつ、ビジネス環境や業務内容の変化などに対応していくことも必要なのだと思います。
横道にそれましたが、その回線数などを試算する際に必要になってくるのが、トラフィックエンジニアリング です。
トラフィックエンジニアリングは、ネットワーク上に流れるトラフィックを効率的に過不足なく処理するために行う設計等の作業になりますが、PBXの設計においては、音声ネットワーク上に流れる一定期間に要求される通話量を伝送するために必要なTrunk数を決定する、ということになります。
トラフィックデータの把握
まず現在の音声トラフィックデータを把握することがスタートです。
通常、PBXは処理した呼の詳細情報が記録されたCDR(Call Detail Record)があります。
そこにはどの内線からどの外線を使って発信をした、などの情報が記載されており、そのデータを一定期間分確認します。
その際に、誰(内線番号)がどんな目的でどのTrunkを使っているか、の分類も可能になるときもあります。
コールセンター用の回線を収容しているTrunkとオフィスで使っているTrunkを分けて使っていれば、それぞれの利用量を分けられるということです。
そして確認できた通信量から必要回線数を算出することになりますが、その際の考え方にトラフィック理論というものがあります。
PBXをはじめとした通信施設の計画・設計・運用の基本的要素として理解されるものですが、PBXの主目的である「通話できる・できないという程度をあらわすサービスレベル」と「設備数」との関係を理論的に体系づけたものともいえます。
そのトラフィック理論における魔の指標がアーランです。聞いたことがある方も多いと思いますが、わかりづらく敬遠したくなるような印象が強いです。
アーランそのものは呼量の単位で、「一定時間でどれほど電話(回線)を使っているかを表すもの」とされており、次の式で算出が可能です。
アーラン(呼量)=最繁時呼数×平均利用時間(回線を占有している時間)÷測定時間
さて、このアーラン。
PBX設計においては「呼量(アーラン)」と、「呼損」がどれほどの頻度で発生するか、によって、必要回線数を導くことが可能になるような理論式があります。
なお、日本のお客様だと、「呼損は発生しない『ゼロ』でしょうが!」という話をされることもありますが、残念ながら必ず発生するという前提のもと設計されます。
100回電話かけて1回つながらない場合は呼損率0.01になります。
当然ゼロに近いほうがコールセンターの窓口としてはよくつながることになりますので、顧客満足の指標のひとつをとらえるとステキなことですが、一方でその分のシステム環境を準備しないといけないため、コストはかかります。
その頃合いをどこでつけるか、ということが必要になってきますね。
ひとつの例として総務省が定めている電話事業者に求める音声品質の要件では呼損率0.15以下になっています。想像以上に厳しくないような気もしますね。
その呼量(アーラン)と呼損率から必要回線を導き出すのが「アーランB」といわれる数式です。数式を見ると見ないふりをする私にはきわめて意味不明なモノが並んでます。
あれ、おでんになっていますね。
このおでん数式の意味合いをお伝えするのは難しいので一気にまとめてしまうと、便利なことに呼量と呼損率から必要回線数を算出してくれる下記のようなトラフィックテーブルというものがあります。
呼損率が0.1(①)、呼量(アーラン)が2.88(②)とすると、必要回線数が5回線(③)と割り出すことがこのテーブルを使うと可能になります。
今やwebサイトに呼量と呼損率を入れれば回線数表示してくれるサイトもあります。お・で・ん!ですぐに算出完了なので、もはや設計はおでんだ!うまく活用しておでん食べましょう。
なお、アーランBというのは呼損としては完全にブロックしてしまう考え方に基づいているのですが、もうひとつアーランCというものもありまして、こちらは待ち行列に並ぶという考えかたに基づいたものです。
コールセンターにおいて電話をかけてきたお客様が待ち呼に入るようなことに通じますので、必要オペレーター数の算出に使われることが多いです。
この少々難解でやっかいなアーランですが、その由来はアグナー・アーランという人物がいらっしゃって、デンマークの通信トラフィック工学および待ち行列理論の開祖です。
幼い頃から本を逆さにして読むことができた、という凡人にはその行動の意味がわからない逸話があるようです。
ちなみに、このアーランは昭和40年にNTT接続基準に制定されたりしていますが、同じ学問を志された方にモリナという方もいらっしゃって、この方の編み出した「モリナ式」というものも回線数算出に使われることもあるようです。
コールセンターですと各種レポート機能もありますので、呼量と呼損についての裏付けとなるデータは取れるのではないかと思います。
ハードウェアの選定
トラフィックから必要回線数が決まれば、あとは「インターフェースをどうするか」と、それに合う「PBXのハードウェアの選定」という工程に入ります。
PBXと電話網をつなぐインターフェースにはいくつか種類があります。
アナログ回線やデジタルの回線、そして今後はIPを活用するサービスを提供している会社も増えていくかもしれません。
2024年問題もひとつのきっかけになるかもしれませんが、そこで話題になっているNTT東西が提供しているISDN回線のサービスINSネットは「通話モード」と「ディジタル通信モード」があるのはご存知でしょうか。
このうちディジタル通信モードが終了になり、一般的に電話用途として使われている「通話モード」は継続して使えるのですね。
NTT東西に触れましたので、NTT東西が提供しているこのINSネットを例にとると、INSネット64とINSネット1500というサービスがあります。
INSネット64は2回線利用することができ、一方のINSネット1500は23回線を利用できるものです。1本の物理的な通信回線を論理的なデータ伝送路に分割して2回線もしくは23回線利用できるようになるのです。
それぞれに対応するインターフェースはBRIとPRIと呼ばれるものです。
ちなみに、日本と例えばヨーロッパではこの規格も違いがあったりしてインターフェースの呼び方も変わったりします。海外製品も多いPBX業界ですから、その違いに慣れないととまどうこともありますね。
算出した必要回線数が10回線であれば、未来の拡張性を考慮いてPRIを1本にしよう、いやBRI5本にする、という議論も出てくるのですね。
ここは算出された必要回線数と、コールセンター用と事務用でTrunkを分けるか否か、将来的な拡張を考慮するか、それぞれの場合の費用はどれほどか、といういくつかの視点で比較検討することが必要になってきます。
次回はPBXの設計におけるアプリケーション関連について触れたいと思います。
Omnia LINK(オムニアリンク)は、クラウド型IP-PBXを基盤としたコールセンター向けトータルテレフォニーソリューションです。基本の通話・管理機能はもちろん、AIを利用した通話音声のリアルタイムテキスト化や、FAQリコメンデーションなど次世代機能を提供します。在宅コールセンターにも対応しています。
以下のようなお客様にお勧めです。
・オンプレ型のPBXからクラウド型に移行したい
・通信費や保守費用などのコストを削減したい
・毎月使う分だけライセンスフィーを支払いたい
・場所にとらわれず、電話が取れる環境を整えたい
詳しい資料は、以下からご覧いただけます。
https://www.bewith.net/gemba-driven/download/entry-126.html
その他関連サービス
■クライアント企業に合わせた、最適運用を実現
コールセンター・コンタクトセンター
■クライアント企業のマーケティング活動を最適化
アウトバウンド
■お客様のニーズに寄り添い、お客様に合わせたミライを提供
インバウンド



 資料ダウンロード
資料ダウンロード
 お問い合わせ
お問い合わせ






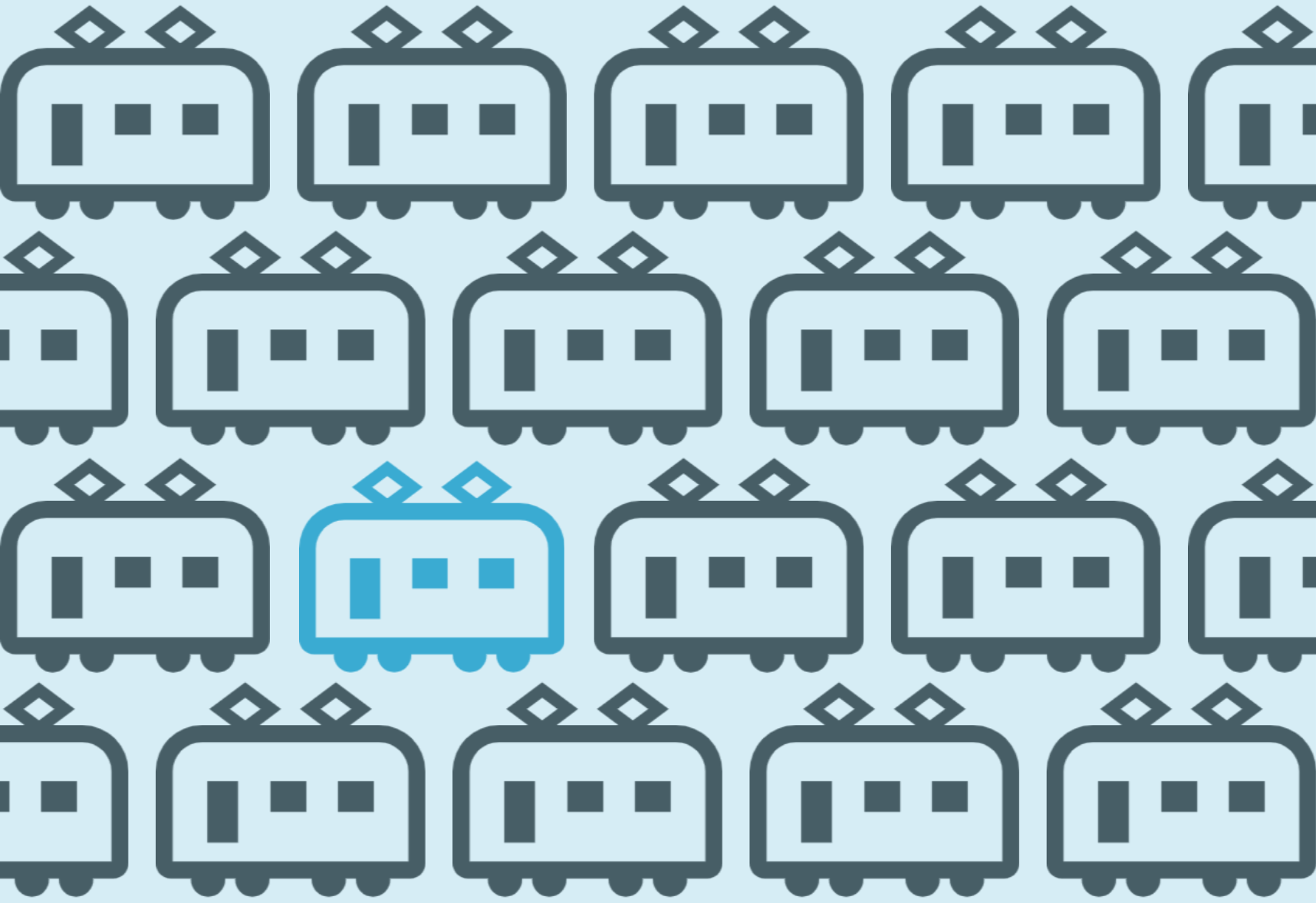

 メールマガジン登録(無料)
メールマガジン登録(無料).png)
.png)




