私の「判断」は、あまり早くない。
若い頃は判断の早い先輩のヒラメキ感に憧れたものだが、いつしか判断が早いのはいつも考えているからであって、ヒラメキではないことを知り、早いことも重要だが適切であることのほうが重要だろうと、早さに憧れなくなってしまった。
私は「行動」も、あまり早くない。
とても自慢できることではない。早く始めればいいのに、時には“やる理由”や“やらない理由”を考えて時間が過ぎ、さらには天からの知らせが舞い降りてくるのを待ってしまう。世が世なら、そうしている間に攻め込まれ、命を失っている。
さて最近、なかなか動き始められなかったことといえば、システムマニュアルの作成だ。
どこからどう作り始めるべきなのか、しばらくモヤモヤしたまま動けず、少し手を付け始めても「なにか違う」と感じて手が止まる。これまでもこういうことは何度かあったが、今回ばかりはシステムマニュアル特有の要因がいくつか重なっているような気がした。
“機能”を知っても動けない、“手順”を知ると“情報”が欲しくなる
昔に比べれば今のシステムはわかりやすい。「“直感的だからマニュアル不要”と謳うシステム」や「マニュアル作成ツール」の登場、「動画」の普及により、お手製でシステムマニュアルを作ること自体への反対意見も聞こえてくるようになった。
それでも、私は「業務用にはシステムマニュアルは必要」だと思い、作り始めたのだが、すぐに「やっぱり要らないのかもしれない」という場面に遭遇してしまった。
なぜなら、私が作り始めたマニュアルが、例えるならばこんな感じになっていたからだ。
・「新規登録」をクリックすると、新規登録できます。
・「クレジットカード」タブは、カード情報の入力・照合ができます。
・「配送会社」を押すと、配送会社が選べます。
そりゃそうだろうよ、言われなくてもわかる。やはり今やシステムマニュアルは必要ないのか。いや、そうではなく、たぶん私の作り方が間違っているんだろう。
そんな時、ある人が言った。
「システムマニュアルを“機能型”で作るか、“手順型”で作るか悩む」
ハッ(・□・;)
それだ。
私は“機能”だけを作ろうとしていたんだ。
ならば、“手順”で考えてみよう。
電話番号検索で新規か確認→新規であれば[お客様情報]タブの[新規登録]を押し顧客情報を登録→次に[注文]のタブに切り替え、商品名、数量を入れる→金額確定→支払い方法確定→クレジットカードの場合は[カード]タブ→配送会社の希望がある場合は[配送]タブ~
“手順”にすると、“機能”よりも流れと動きがわかるようになり、行動できそうになってきた。でも今度はたくさん疑問が湧いてきた。
・支払い方法にはどんな方法があるの?
・どういう時に配送会社を選んでいいの?
“手順”にしたら、今度は“知識・情報”に不足を感じるようになった。
業務システムマニュアルに求められる4要素
ここまでに「業務システムマニュアル」に求められる3つの要素が見えてきた。
① システムが持つ機能を知ること
② システムを操作する手順を知ること
③ 業務を遂行するための知識・情報も同時に知る必要があること
そしてこれに、もうひとつ
④ 旧システムとの違い(本来の使い方との違い)
を加えることにする。
なぜなら、昨今「はじめてのシステム導入」というケースは少なく、ほとんどの場合「システムのリプレイス」だからだ。実際、今回の私のモヤモヤの要素のひとつはコレであった。新しいシステムに変われば全体的な利便性は高まる。
しかし残念なことに「できたはずのことが、できなくなる」ことも少なくない。さらに時にそれは、容姿も性格も考え方もガラリと変わった別人のようで、新しいシステムとの付き合い方がわからなくなってしまう人がいる。付き合ってきた期間が長ければ長いほど、使い手にとって頭の切り替えが困難であることを、経験上、知っていたから「違い」を知ることも、ひとつの要素として加えることにする。
また、リプレイスでなくても、パッケージ製品の場合、そのシステムの本来の主旨とは少し異なる特有の使い方をすることもある。これもある意味では「違い」として整理した。
4要素を同時に考えるとややこしい、ひとつずつ明らかにしていけばよい
4つの要素が見えてきたので、次に、どんな構成にして作成を進めていったのか、説明していこう。
まず、マニュアルの冒頭で、どんな機能があるか全体をおおまかに説明することにした。当たり前のことを羅列するだけのつまらない内容になることもある。しかし、初めてシステムに触れる読み手にとって、全体理解から始められることは大きな安心材料となる。
次に旧システムとの違いや自社特有の使い方(本来との違い)を説明する。旧システムを知る者にとって、ものすごく気になる点なので、先に疑問を解消しておく。そして、おおげさに言えば、読み手に「旧から新に、考え方を切り替えなくてはいけない」という覚悟をしてもらうという意味も込めて冒頭にした。
機能や違いの説明は、システム全体の性格を知ってもらうことが目的なので、さらりとで良い、動画でも良い。
本編は手順をメインに構成するが、各ページに他の3要素(機能、違い、情報)も入れることにした。親切すぎるような気もするが、機能や違いは冒頭のページの繰り返しであるし、情報も事前に整理できているので、作成にはそれほど時間はかからなかった。
そしてメインである手順こそ、実は作るのはとてもラクだった。システムのUI(見た目や使いやすさ)が優れていれば、マニュアルで多くを語る必要がない。画面のスクリーンショットの貼り付けを作業的に繰り返すか、またはシステム会社から提供された操作マニュアルや、マニュアル作成ツールも役立つだろう。
このように4つの要素で整理したら、モヤモヤが晴れて、作業自体はスムーズに進んだ。作業も後半になってくると、説明が重複する部分があったり省略できる箇所も増えてくる。作成の途中では「やっぱりマニュアル要らないかも」と思ったりもしたし、仲間の「マニュアルなんて誰も見ない」という囁きも聞こえてきたが、挫けず進めた。そして、システムマニュアルは、まぁまぁ立派なボリュームとなり、「業務システムマニュアル」は完成した。
業務システムの“業務側”と“顧客側”
業務システムには“業務側”と“顧客側”がある。
業務側は多機能だからマニュアルを作れば、今回のように、結局かなりのボリュームになる。一方で顧客側に見える部分は、機能を絞っているから直感的に入力できるよう設計されている。画面がわかりづらければ顧客は離脱する、何度も駅員を呼び出す。だから、そうならないよう上手く設計されている。
おかげで私は、駅員に質問することなく券売機で切符を買うことができる。座席の指定だってできる。指定席は窓口でも買える。その時、窓口の人はたくさん何かのボタンを押す、券売機で何度か画面を切り替えているっぽい動作をする。出てくる切符は同じなのに、窓口の人が操作する業務システムはとても難しそう。きっと分厚い「業務システムマニュアル」で習ったはずである。
窓口でその操作を眺めながら「たくさん押してるな~」と思ったことがこれまで何度もあったが、この度、窓口の人がたくさん押す理由がちゃんとわかった。
そして、あぁやっぱり、業務側の「システムマニュアル」は必要だよなぁと思った。
当社は、コンタクトセンターの構築・運用・改善・高度化の手順を、最新の動向を踏まえて豊富な図や事例で解説した書籍 『図解でわかるコンタクトセンターの作り方・運用の仕方』 を、株式会社日本実業出版社より発刊しています。
本書では、コンタクトセンターを最初に立ち上げる際に熟慮しておくべきこと、日々の運用の過程で次々と出てくる課題や改善の高度化要望の実現を効率的に進めていく手法等、コンタクトセンターの構築・運用・改善・高度化の進め方から、スタッフ育成、最新テクノロジー活用方法まで、151の図解と31の先進事例、効果がわかる実態データも含めて、詳しく説明しています。
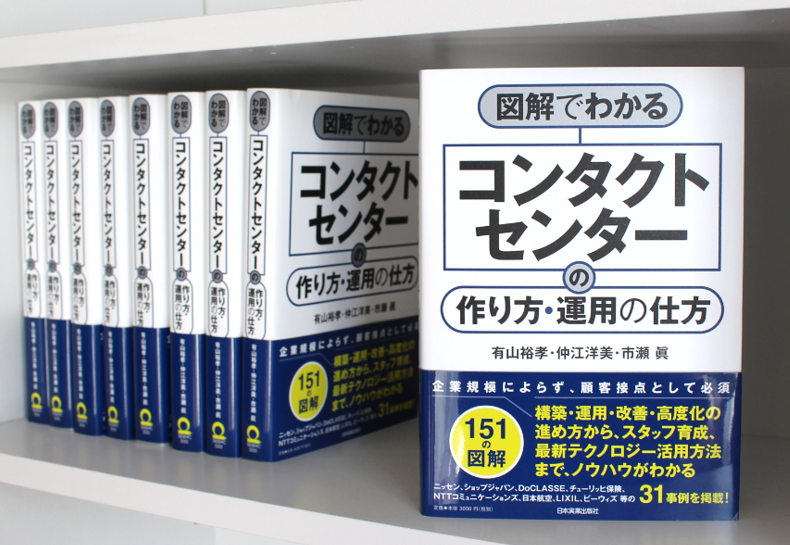
オペレーターから始めて、コンタクトセンター業界で早20年。まさかのコンタクトセンター本を出すことになりました。 | HUMAN | オペレーションを進化させる現場のWebマガジン 現場ドリブン
現場ドリブン
2月27日に、私が、その一部を書きました『図解でわかるコンタクトセンターの作り方・運用の仕方』が出版されます。本書は、長年にわたりコン



 資料ダウンロード
資料ダウンロード
 お問い合わせ
お問い合わせ




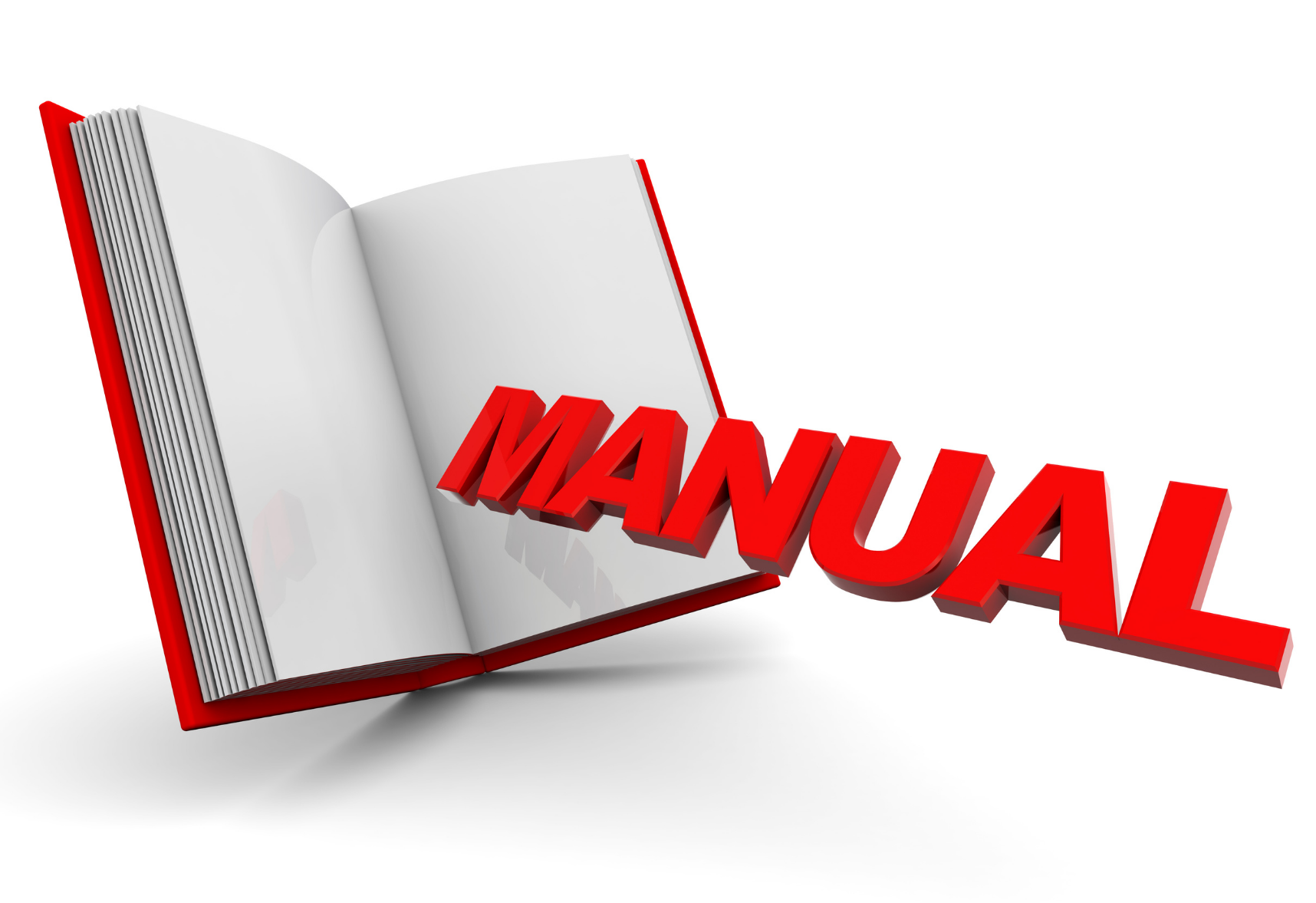

 メールマガジン登録(無料)
メールマガジン登録(無料).png)
.png)




