もう5年以上も前になるだろうか。
大学卒業後ドイツに移住したわたしは、異国の地でどうにか手に職をつけようと、Ausbildung(以下:アウスビルドゥング)に申し込んでいた。
アウスビルドゥングとは、職業学校に通いながら訓練生として働く、ドイツの職業訓練システムである。
たとえば、美容師になりたければ、週2日美容専門学校に通いながらそれ以外の日は美容院で働く……というイメージだ。
当時からわたしは文章メディアに興味があったものの、いかんせんドイツ語ノンネイティブ。さすがに「書く」分野はムリだろうと、ホテリエを目指していた。
そこで申し込んだのが、フランクフルトのとある高級ホテルのアウスビルドゥング。
ドイツで働いた経験がなかったわたしにとって、はじめての挑戦だ。
しかしそのアウスビルドゥングは、とんだ「ハズレ」だった。
試し働き開始!でもなんだか様子がおかしいぞ?
アウスビルドゥングに申し込み面接をパスしたわたしは、1週間の試し働きに招待された。1週間実際に働いてみて、その後採用か否かが決まる。
試し働き中は無給とはいえ、ドイツでの初仕事。緊張で胃がキリキリと痛むなか、朝5時に起床。ホテルで必要になりそうな専門用語を書いた単語帳を携え、いざ出陣!
アウスビルドゥングにはさまざまな決まりがあり、実施する企業には必ず、訓練生の面倒を見るAusbilder/in(アウスビルダー)がいる。「監督官」とでも訳せばいいのだろうか。
ホテルのフロントで「アウスビルドゥングの試し働きに来ました」と言うと、さっそくその監督官の部屋に案内された。
自己紹介もほどほどに、ランドリールームへ移動。監督官は「午前中はこの人と客室清掃してください」と、ひとりの女性を指名した。
その女性は不思議そうな顔をしながら、「じゃあついてきて」と自分の仕事を開始。
彼女はドイツ語があまり得意ではないようで、わたしたちはほとんど会話をしなかった。そもそも清掃員としてここに来ているだけで、ホテルの人ではないらしい。
お昼になり休憩室でご飯を食べた後、見ず知らずの人に呼ばれたかと思ったら、「午後はこの子と働いてね」と言われる。紹介されたのはブロンドヘアの女の子で、アウスビルドゥングの訓練生とのこと。
午後は彼女といっしょに各フロアを掃除機できれいにし、ホテル近くに残された路上生活者の寝床を撤去し、その後は黙々とホテルの周りの芝生の上の落ち葉を拾った。
そして、試し働き1日目が終了。
「初日ならこんなもんだろう」と深く考えず、家に帰りその日の様子を友人と当時の彼氏(現夫)に報告。すると、全員がこぞって顔をしかめた。
「そんなんじゃホテルの仕事を経験できないじゃん」
「外部の清掃員は清掃が仕事なんだから、訓練生の面倒を見るのは契約外でしょ」
「ホテルの仕事を見せてあげようって気持ちが全然ないよね」
と批判するのだ。
ドイツで働いた経験がなかったわたしは、「よくわかんないけど、なんかヘンなことなのかなぁ?」と、そのときはのんびり構えていた。
わたしの担当監督官が上司に怒られた!理由は……
翌日もふたたび朝5時に起床し、靴擦れの痛みに耐えながらフランクフルトに向かう。
前日「明日はレストランに行って」と言われていたので直接レストランに行き、「試し働き2日目よろしくお願いします!」と元気に自己紹介。
しかしそこで、「え、聞いてないんだけど」と言われてしまう。
「だれか聞いてる?」「いや知らない」「ふーん。じゃあまぁ、洗い場でもしといてもらおうか」と言われ、わたしは洗い終わったコップやお皿を所定の位置に戻すという仕事を与えられた。
とはいえ、10分前に到着したばかりの初めて来るレストラン。どこになにがあるのかなんて、まったくわからない。
みんながそれぞれ仕事をしているなか、「このお皿はどこに運べばいいですか」「このコップはどこですか」と毎回聞かなきゃいけないので、とても申し訳ない。でも聞かないわけにもいかず……。
そんなこんなで午前中終了。
さて、午後はなんの仕事かと思っていたら、とくに指示がない。
キッチンのリーダーっぽい人に「なにをすればいいですか」と聞いたところ、「じゃあ食器拭いといて」と言われ、わたしはその後時間いっぱい、キッチンの隅っこで、ひとりでフォークとナイフを拭いていた。
……さすがに、ちょっと変じゃない?
家に帰って彼にその日のことを話したところ、ふたたび「それはふつうじゃない」と即答された。
「試し働きはいろんな仕事を見せて職場の雰囲気を知ってもらうためのもので、タダで雑用をさせることじゃない。そんなんじゃホテルの仕事を理解できるわけがない」とのこと。
ちょうどこの会話の直後、彼の親戚から「試し働きはどうだい」という電話がかかってきた。
実はこのアウスビルドゥング、ホテルの人事として働いている夫の親戚の紹介だったのだ。
夫が「今日は丸一日、ひとりで食器を片付けたり拭いたりしてたらしいよ。訓練生が来ることを現場は知らなくて、まともな仕事をさせてもらえなかったみたい」と言ったところ、親戚の人もびっくり。
スマホ越しに、「なんだそれは!」という声が聞こえてきた。
わたしの監督官だった女性は、その後上司からめちゃくちゃ怒られたらしい。
(後日彼女から丁寧な謝罪メールが届いた)
「新人育成は担当者の業務」という認識
「先輩が後輩の面倒を見る」という日本のやり方に慣れていたわたしは、「じゃああとよろしくね」とレストランに放置されても、なんの違和感ももたなかった。
先輩自身にも仕事があり、片手間に後輩を気遣ってあげる。後輩が困ってたらフォローして、勉強になりそうなら一緒に連れて行ってあげる。
わたしにとって「社員教育」とは、先輩が後輩の面倒を見る、いわば部活のようなイメージだったのだ。
しかし彼や友人、彼の親戚などの反応を見ると、どうやら彼らの考えはちがうらしい。
ドイツでは、「訓練生が予定どおりの仕事を経験できているか」「職場の人がちゃんと面倒を見ているか」と気にかけるのは、先輩の『善意』ではなく、監督官の『業務』なのだ。
だから、「職務放棄」ともいえる監督官の仕事ぶりに、違和感を覚えたのだろう。
彼には「なんで途中でその人のところに行って、『他の仕事をください』と言わなかったの?」と聞かれたが、試し働きなのにそんなことを言うなんて、わたしは考えもしなかった。
そう答えると、「なにに遠慮してるの? 君は仕事を学ぶために行ってるんだし、それを采配するのはその人の仕事なのに」と首をかしげられるくらい、わたしたちの考え方はちがっていたのだ。
名プレイヤーが名監督になれるわけではない
ドイツには日本のように、ノースキルの学生を採用して会社で育てていく、という考えがない。
このアウスビルドゥングだって、「企業は安く労働力を確保できる」「求職者は経験を積んで就職につなげられる」という利害の一致で成り立っている、というだけの話だ。
愛社精神を求めることもなければ、先輩としての頼りがいなんてのもアテにしない。
社内教育は、ビジネスライクでシステマチックな「業務」。
だから他の業務と同じように担当責任者がいるし、その人が仕事をしていなければ怒られる。
一方で日本は、新人の教育は先輩の「善意」に甘える部分が大きいと思う。「後輩の面倒を見てあげてね」と。
そこでふと、25歳を越えたあたりから、日本の友人たちが口々に「教育係になって困っている」と話していたことを思い出した。
「自分の仕事で忙しいのに後輩の面倒なんて見られない」
「マニュアルがなくて自己流でやってたのに教えるとかムリ」
「なにを教えるべきなのか指示されてないのに任せられても困る」
などなど。
そりゃまぁ、「教える」ことが仕事じゃないのに「後輩の面倒を見てやって」と新人育成を丸投げされたら、本人は困るよなぁ。
教えることで本人が学べることがあるとはいえ、プレイヤーはあくまでプレイヤー。
「名プレイヤーが名監督になれるわけではない」という表現があるように、だれかになにかを教えるというのは、それ自体がひとつのスキルだ。
そのスキルがない人に任せたら、思うようにいかないのは当然である(教えること自体はその人の仕事ではないので、そこに適性がないことは本人の責任ではないだろうし)。
では、だれかになにかを教えるには、なにが必要なのだろう。
どうすればわたしの試し働きは、うまくいったのだろう。
人材育成に必要なのは、「先生」「計画」「監督」
教育機関といえば、まっさきに思い浮かぶのは学校だ。
学校では、大学などで教え方を学び資格をとった「先生」が、大人数で時間をかけて決めたシラバスという「計画」に沿って授業をし、校長や教育委員会などの「監督」がそれをチェックすることで成立している。
スポーツも、綿密に組まれたスケジュールがあり、それに合わせてコーチがトレーニングし、監督が最終決定する。
そう考えると、ホテルでの一件は、全体を仕切る「監督」が自分の仕事を怠り、現場は「計画」がないままわたしを受け入れ、最適な「先生」がいなかったから、わたしはなにも学べなかった……といえそうだ。
(外部の清掃員や訓練生がわたしを「教育」できないのは当然のことであり、そのふたりには責任はない)
社内での人材育成も学校教育やスポーツと同じで、ガイドラインとしての「計画」を基に、教え方を学んだ「先生」がそれを実行し、責任者となる「監督」が総括する。そういうシステムが必要なのだろう。
もちろんそれは、「善意」ではなく、「業務」で行われることを前提として。
それを学べたという意味では、早起きして一日中キッチンで食器を片付けたり拭いたりしたのも、いい社会経験だったかもしれない。
ライタープロフィール
雨宮 紫苑
ドイツ在住フリーライター。Yahoo!ニュースや東洋経済オンライン、現代ビジネス、ハフィントンポストなどに寄稿。著書に『日本人とドイツ人 比べてみたらどっちもどっち』(新潮新書)がある。最近飼い始めた犬にメロメロ。



 資料ダウンロード
資料ダウンロード
 お問い合わせ
お問い合わせ




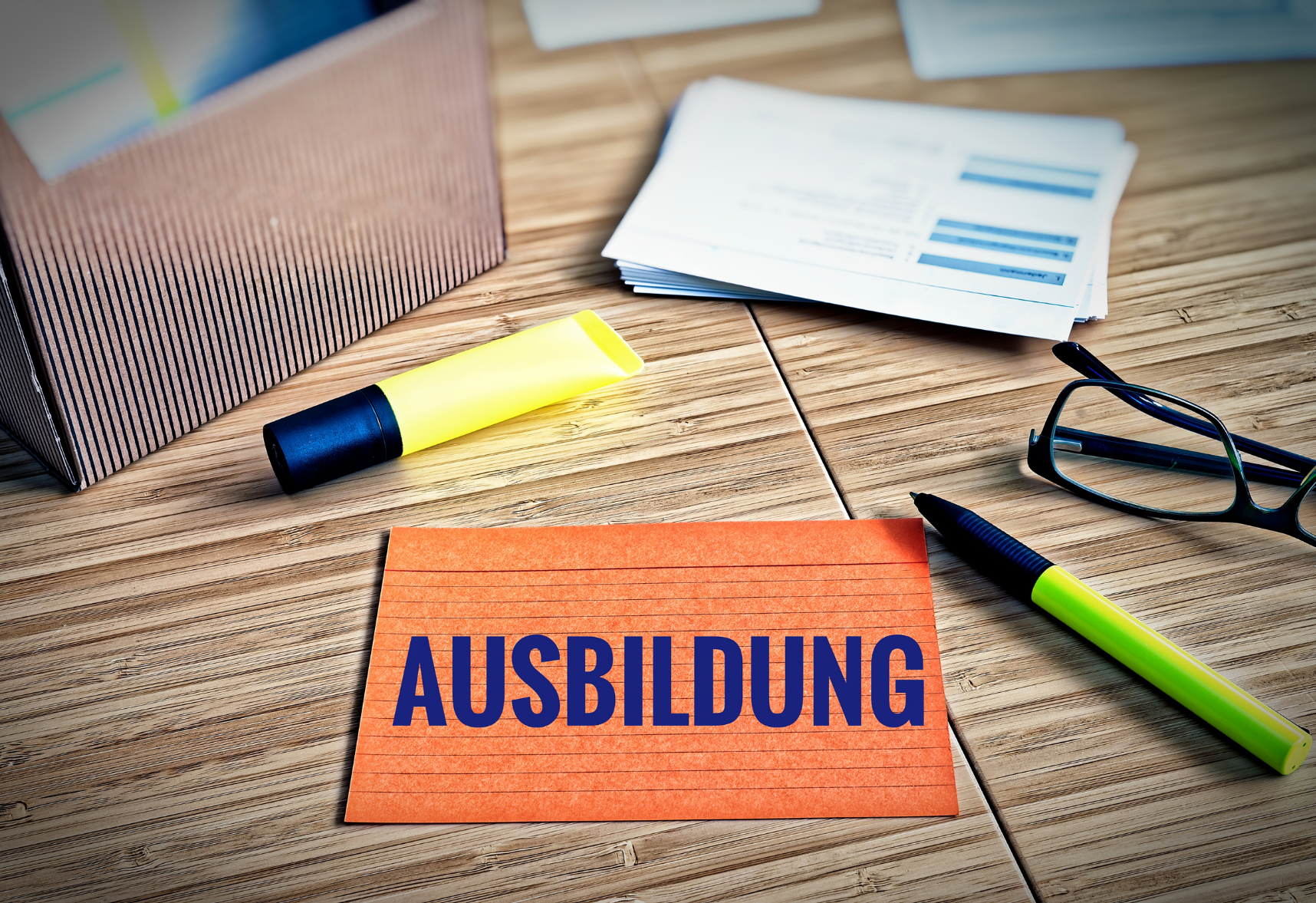
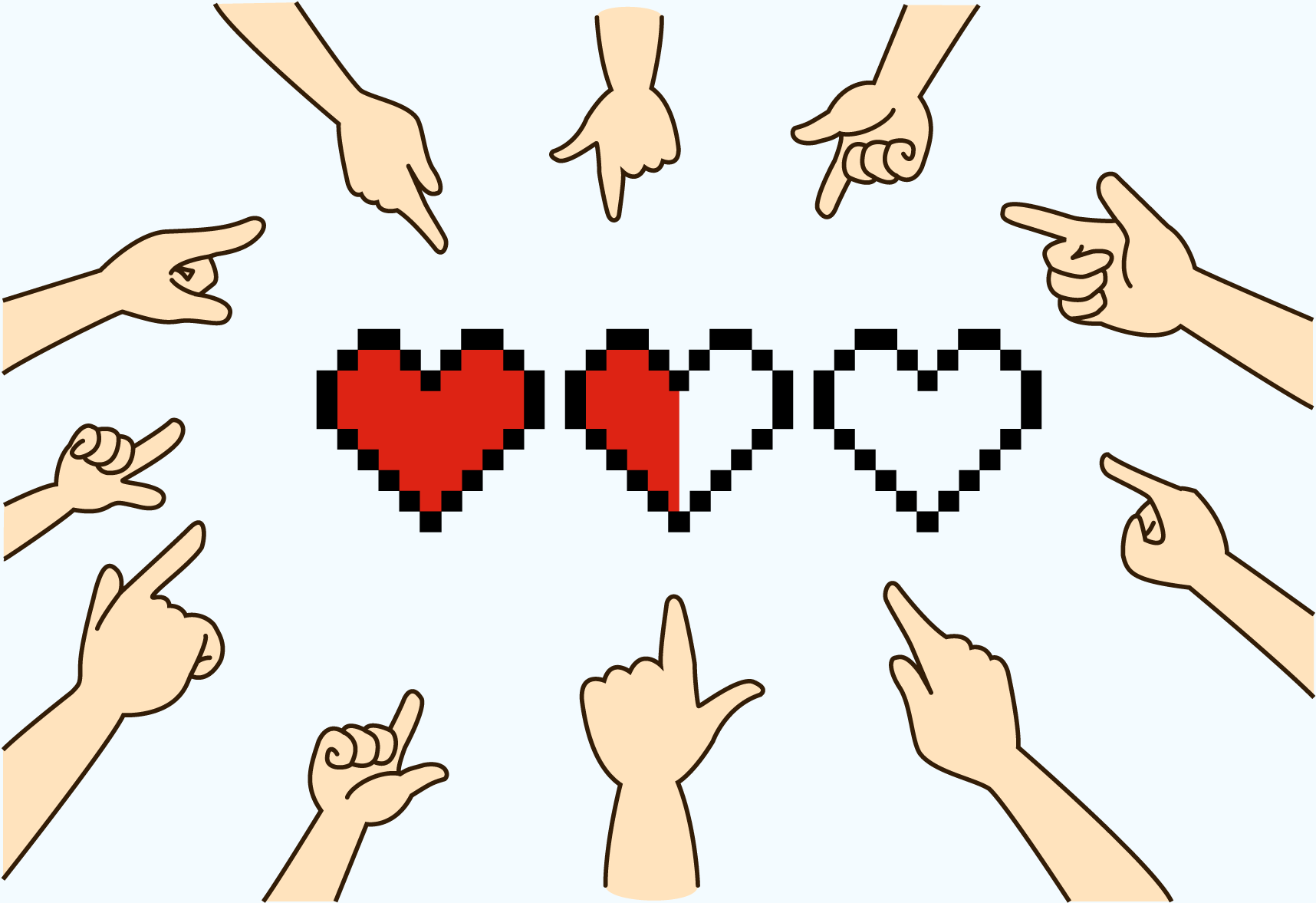
 メールマガジン登録(無料)
メールマガジン登録(無料).png)
.png)




